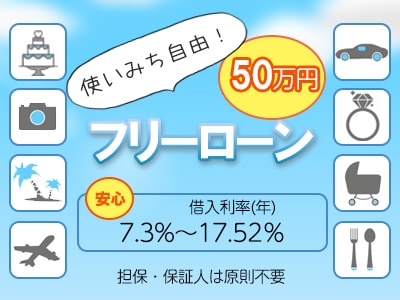確定申告の必要性の有無とは?特徴や行わないことによるリスクも解説
確定申告の必要性の有無は人によって異なるため、申告の必要がない方もいます。しかし、申告を行わない場合、ペナルティを受けてしまうケースもあります。では、どういった方が確定申告の対象となるのでしょうか。今回は、確定申告の特徴、必要性の有無や行わないことによるリスクについてみていきましょう。
確定申告の特徴
確定申告の特徴は以下の通りです。
・確定申告とは
所得税における確定申告とは、1年間の所得をとりまとめたうえで、所得にかかる税金を計算し、税務署などに納める税額を報告する手続きです。1年1回行い、1月1日~12月31日までの所得と納める税額を計算します。
例えば、2021年の確定申告では、2020年1月1日から2020年12月31日までの所得と納付する税額の計算が必要です。
・期限や時期
確定申告の期限や時期については、原則として所得を報告する年の翌年の2月16日~3月15日までの間に税務署に報告し、税金を納税する必要があります。ただし、2021年の確定申告は、コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、2月16日~4月15日まで期限が延長されている点は把握しておきましょう。
確定申告の必要性の有無

確定申告の必要がある人とない人の違いは以下の通りです。
・必要な人
確定申告は原則として、年間の所得金額から所得控除額を差し引いたうえで、金額がプラスになる場合は確定申告が必要です。例えば以下のようなケースがあてはまります。
・年末調整がある会社員でも年間の給与収入が2,000万円を超える
・給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える
・フリーランスや自営業などの個人事業主の方で所得が基礎控除額(48万円)以上ある、
・副業の収入が20万円を超えている方
今回、紹介した以外にも所得を得ることで確定申告が必要となるケースがあるため、条件に該当するかどうかを確認することが大切です。
・必要がない人
公的年金を受給している人は、基本的に確定申告は必要ありません。ただし、公的年金の収入が400万円を超える場合やそれ以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要なので注意しましょう。
また、1つの企業に勤める会社員であれば、会社が年末調整を社員に代わって行ってくれるため、確定申告が不要です。ただし、年収や副業収入が一定額を超えた場合、2カ所以上からから給与を受け取っている場合は確定申告が必要であるため、注意しましょう。
確定申告を行わないことによるリスク
確定申告が必要であるにも関わらず、行っていない場合は、以下のようなリスクがあります。
・無申告加算税や延滞税を課される
確定申告の期限内に申告しなかった場合や無申告の場合、納税額に応じて税金が課されます。延滞税は、納めるべき税金を納付期限までに納めない場合に課され、納税が遅れた日数分だけ金額が加算される点に注意が必要です。
それぞれに課される金額や年率は以下の通りです。
| 無申告課税 | 延滞税 |
| 納税額が50万円以下:納税額の15% | 法定納期限の翌日から2ヵ月以内:「年7.3%」、「特例基準割合+1%」で低い方の割合 |
| 納税額が50万円以上:納税額の20% | 法定納期限の翌日から2ヵ月以上経過:「年14.6%」、「特例基準割合+7.3%」で低い方の割合 |
| 税務署の調査通知を受ける前に自主申告した場合:5% |
無申告で悪質な所得隠しや課税逃れだと税務署に判断された場合、納税額の40%となる重加算税が課税されます。脱税とみなされた場合、刑事罰に処される可能性も想定しておきましょう。
・課税以外にもペナルティを受ける
確定申告を期限内に行わない場合、還付金を受け取れないだけでなく、融資の審査に通りづらくなります。また、2期連続で期限後の申告を行った場合、青色申告の特別控除55万円が10万円に減額されるなどのデメリットがあります。
また、無申告であれば、税務署などからの通知が送られてくることがほとんどです。しかし、通知を無視した場合には、給与や自宅など財産の差し押さえが行われるため、無申告状態での放置は厳禁です。
確定申告が節税に繋がる場合もある
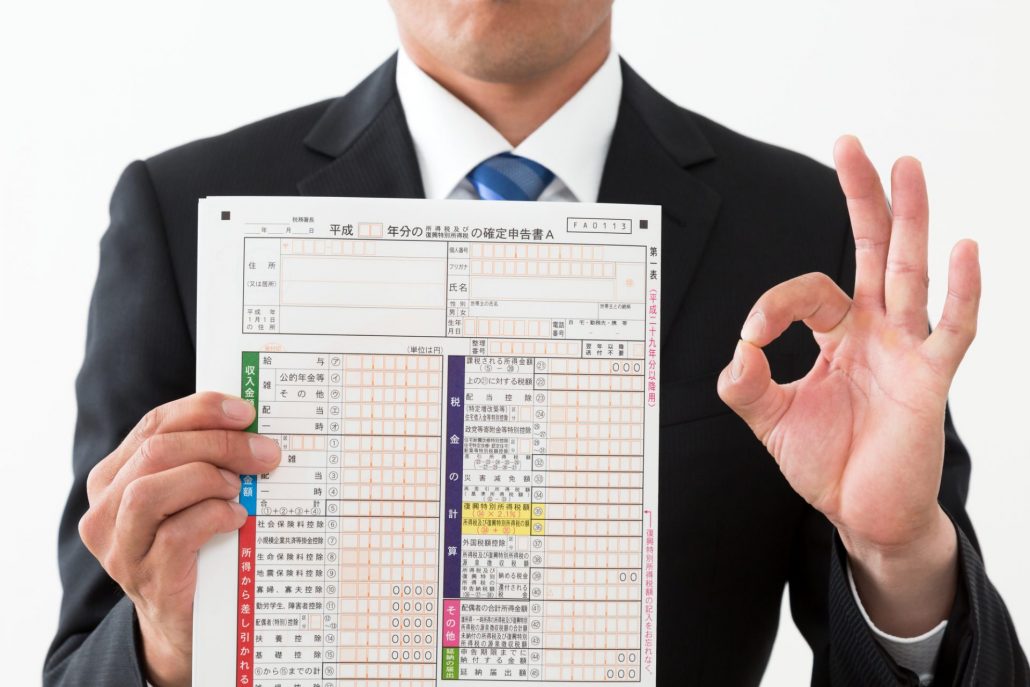
個人事業主の場合、確定申告の際に事業所得と必要経費を申告します。この申告の際に、青色申告を行うことで課税所得を減らせるため、節税に繋がります。
青色控除では以下のようなメリットを受けることが可能です。
・青色申告特別控除が使用できる(10万円~65万円の所得控除を利用できる)
・事業の必要経費を計上することで、所得額が減少する
・固定資産税などの税金を必要経費にできる
この他にも数多くのメリットを受けられるため、個人事業主で白色申告を行っている方は、青色申告への変更を検討しましょう。