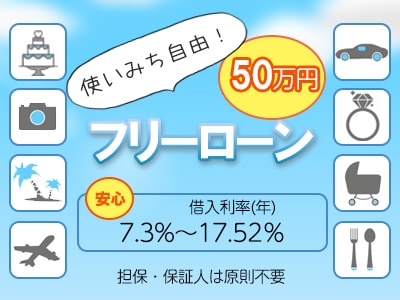不動産登記の構造って何?
不動産登記の際に目にする「建物の構造」という言葉は、建物の登記事項のひとつではありますが、具体的に何を表しているのでしょうか。今回は、建築の不動産登記を行う目的から、申請するべき事項である建物の種類、そして建物の構造についてご紹介します。
不動産登記の目的
建物の構造は、不動産登記の際の登記事項のひとつです。建物が完成した際には、法務局にその建物についての申請書類を出さなくてはなりません。また、新たな建物を建てた場合のほか、その建物に変更があった場合にも申請する必要があります。例えば、家を改築したことでその総面積や構造に変更が生じたときなどです。
不動産登記においては、国民の財産であるそれぞれの不動産(土地や建物)がどこにあって、どのくらいの広さで、どのように使われ、誰が所有しているのかということを確認することで不動産の情報が公示されます。これにより、国民の権利が守られるとともに不動産取引もしやすくなるのです。
書類を申請すると、登記担当者(法務局の職員)が専門的な見地から、実際の建物を確認した上で記載内容に相違がないかを判断します。問題がなければ、その情報はコンピュータに記録され管理されることになります。
・不動産登記の見方のポイント
不動産登記簿謄本は、表題部、権利部(甲・乙)、設定されている場合は共同担保目録の4部構成となります。記載された内容を正確に把握するには、それぞれの役割や意味をある程度把握しておく必要があります。詳しく見ていきましょう。
表題部では、不動産の基本的情報が記載されており、土地と建物で記載項目が違います。権利部では所有権について記載されている甲区を見れば、過去や現在の所有者が把握可能です。乙区は所有権以外に誰がどのような権利を有しているか明記されているのが特徴です。
共同担保目録は、抵当権を設定したときに担保として提供された不動産がある場合、それらをまとめて記載します。そのため、中古住宅などを購入するときに登記簿謄本を確認する場合は、土地・建物それぞれの抵当権だけでなく、共同担保目録の内容が合致しているか確認しましょう。トラブルをさけるためにも大切な要素です。
ただしマンションの登記簿謄本は、土地の情報も建物の登記簿謄本に集約されています。そのため、特別な事情がない場合、建物の登記簿謄本を確認するようにしましょう。
建物に関する登記
建物に関する登記事項には、「所在・地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」があります。建物の「種類」についても、簡単にご説明しましょう。なお、ここでの「種類」とは、建物の利用状況のことを指します。
建物の「種類」については、不動産登記規則第百十三条にて以下のように定められています。
『建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。』
(引用:不動産登記規則第百十三条)
・登記で定義される建物とは
不動産登記法における建物に関しては、準則の136条第1項において、「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」と規定されています。
つまり建物として認められるには、「屋根及び周壁などの外気を分断するものがある・土地に定着している・用途をもったある程度強固な建物である」といった条件を満たさなければなりません。
そのため、1方向にしか壁がないものは登記上で建物とは認められない点に注意が必要です。また、コンクリートブロックの上に置いた建物などは、屋根・周壁・外気分断性があるものの、定着性がないため登記できません。
建物の構造とは
不動産の登記事項のひとつである建物の「構造」については、不動産登記規則第百十四条にて以下のように定められています。
『建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)』
(引用:不動産登記規則第百十四条)
つまり、家を改築するにあたって、例えば木製からコンクリート製に建て替えたり、屋根に使う素材を変更したりした場合には、その旨を変更するための登記を申請する必要があるということになります。「階層による区分」については、地下室がある家の場合には、仮に地下1階がある2階建てであれば「地下1階付2階建て」となります。屋根の種類がこのようにたくさんあることに驚いた方もいるかもしれませんが、この中で特によく見られるのは「かわらぶき」ですね。
建物の種類、建物の構造ともに細かい区分がありますが、不動産登記とはその建物を正しく表記し、見る人がすぐにわかりやすい状態にするものです。不動産登記に関するこうした知識は、自分が家を建てたり、または改築を行ったりすることはもちろんのこと、不動産取引を行う際にも役に立つでしょう。
・建築材料が2種類以上となる場合の表記
建物の構造の中で、構成材料による区分は木造、鉄骨造などと区分して定めます。しかし、構成材料が2種類以上となる場合、実務上の扱いとして、全体に占める割合が30%に満たない場合、その材料は登記しません。
一方で30%を超える場合には、それらの材料を併記して登記することになります。
例えば、木造の割合が90%、鉄骨の割合が10%ならば、「木造」として登記されます。また、木造が50%、鉄骨の割合が50%である場合は、「木・鉄骨造」として登記することになるため、材料の比率には注意しましょう。
木造と木・鉄骨造では固定資産税の評価額や登録免許税額が異なりますので、材料の割合を把握しておきましょう。
まとめ
建物の構造は、不動産登記の登記事項の1つです。建物が完成する・売買されるなど、変更があった場合は、法務局にその建物についての申請書類を出す必要があります。
また、建物の種類や構造には細かい区分があります。不動産登記はその建物に関する情報を表記し、それを見る人がわかりやすい状態にするためのものです。
不動産登記に関する知識を身につけることで、家を建てたり、または改築を行ったりする場合だけでなく、不動産取引を行う際にも役立てられます。