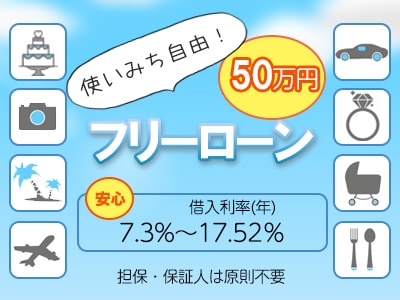二番抵当でも通る?不動産担保ローンの仕組みや通るためのポイントを紹介
抵当権は1つの不動産に対して複数設定できます。しかし、弁済の優先度の順位が最も高い一番抵当から順位が下がるごとに優先弁済の効力は低下します。そのため、二番抵当では不動産担保ローンを借りられないのではと感じている方もいるでしょう。
今回は、一番抵当と二番抵当との違い、二番抵当で不動産担保ローンを利用する際の注意点やローンに通るためのポイントについて解説します。
一番抵当と二番抵当どう違う?
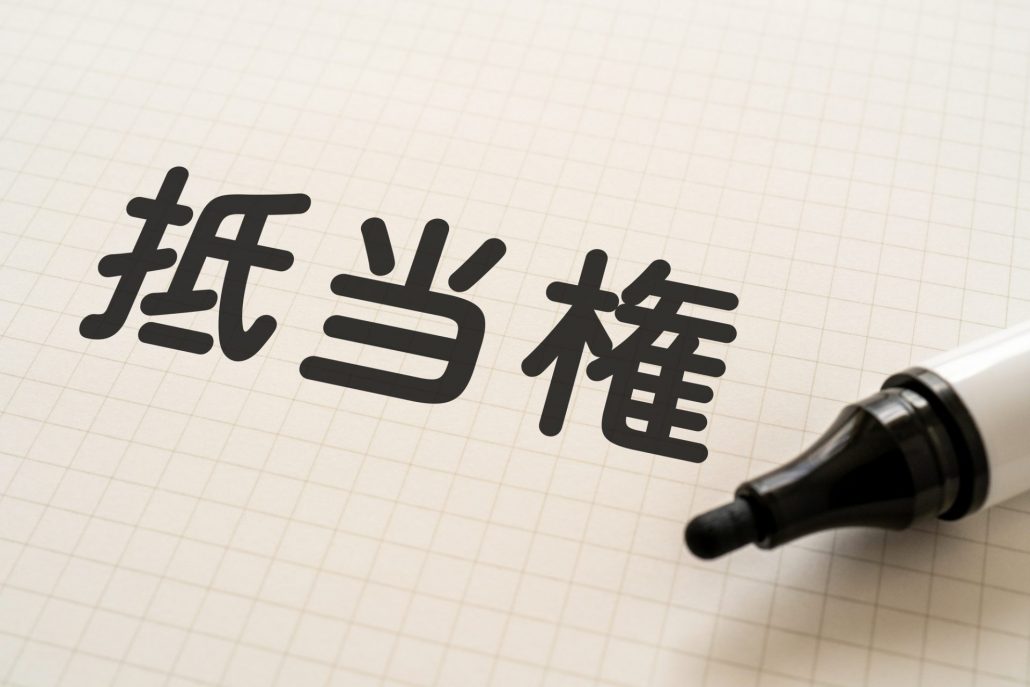
しかし、一番抵当の債権額が担保物件の価値を超えると判断される場合には、抵当権実行自体が取り消されるケースもあります。そのため、確実に弁済を受けられる一番抵当とは違い、二番抵当では弁済を受けられない可能性があるといえるでしょう。
二番抵当でも通るローンの仕組み

ここでは、二番抵当でも通るローンの仕組みをみていきましょう。
ノンバンク系の金融会社や信販会社
ノンバンク系の金融会社や信販会社は、銀行などと比べ審査が通りやすいです。ノンバンク系の金融会社は手続きが簡便で審査が迅速な点が特徴といえます。しかし、上限金利が18.0%程度と高めに設定されています。
信販会社は主なサービスとして、クレジットカードの発行やショッピングローンの提供を行っている会社です。信販会社を利用する場合は、商品代金を一旦立て替えてもらい一括や分割で返済を行います。
ノンバンク系の金融会社や信販会社では、不動産を担保として融資が受けられる可能性が高いといえるでしょう。
不動産担保への評価額で変わる場合がある
一番抵当の不動産評価額が高い場合、二番抵当でも金融機関は貸付リスクをカバーできると判断されやすい傾向です。そのため、高い資産価値を持つ物件を担保にすれば、二番抵当でもローン審査に通りやすくなります。
二番抵当の不動産担保ローン利用の注意点

ここでは、二番抵当の不動産担保ローンを利用する際の注意点をみていきましょう。
担保価値が低いと判断される
二番抵当の場合は、貸付金を回収できないリスクが高いと判断されます。また、担保価値が低いと判断されるため、二番抵当を担保として認めていない金融機関も多く、融資額が低くなりがちです。
全額回収ができないリスクがあることから、金利が高く設定される傾向にある点も知っておきましょう。
希望通りの融資額にならないことがある
二番抵当権者が回収できる金額は、一番抵当権者の債権を回収後の残余資産に依存します。そのため、融資額が制限されるケースが多く、希望通りの融資額とならないことも多いといえるでしょう。
抵当権抹消手続きの手間が発生する
ローンを完済した場合は、担保として提供した不動産から抵当権抹消の手続きを行わなければなりません。抵当権抹消の手続きは無料ではなく、費用がかかります。
費用は抵当権の数だけ必要となるため、二番抵当を設定した場合、一番抵当だけの場合と比較して、抹消手続きの費用が増加する点は知っておきましょう。また、二番抵当の抹消には、一番抵当の方の同意が必要になるため、手続きが複雑で手間がかかります。
二番抵当の不動産担保ローンに通るためのポイント

ここでは、二番抵当の不動産担保ローンに通るためのポイントをみていきます。
不動産が担保担当エリア内にあるか確認
ローン会社が取り扱い可能なエリア内に担保とする不動産があるのかを事前に確認しておきましょう。担保にする不動産の場所が申し込みを検討していた金融機関の取り扱い対象外のエリアとなるケースがあるためです。
エリアを指定しない例はまれで、担保として取り扱えるエリアは金融機関ごとに異なります。HPなどで対象エリアが掲載されているかチェックし、詳細が分からなければ、電話などで担保とする不動産の所在地や住所などを伝えて確認しましょう。
ローン返済の残債はなるべく返済しておく
住宅ローンが残っている場合は、ローンの残債を減らせば、審査に通過する可能性が高まります。住宅ローンの残債が少ないほど、二番抵当が回収できる金額が多くなるため、不動産担保ローンの利用を検討している場合は、繰り上げ返済などを行ってローンの残債を減らしておきましょう。
提出する審査書類に不備がないか確認
審査を受けるタイミングでは、金融機関から要求された書類に不備がないか確認しつつ、指定された期限内に提出しなければなりません。不動産担保ローンは、申し込みから契約時までに用意する書類が多いため、余裕を持って書類を準備するようにしましょう。
書類の不備・不足がある場合、審査がスムーズに進まず、金融機関側で正確な評価や判断ができません。その結果、希望額の融資を受けられない、審査に通らない場合もあります。そのため、提出前の不備や不足がないか、あらかじめ確認しておきましょう。
正しい事業計画書を作成する
事業計画書は金融機関が借入を行う方や法人に対して、将来性や信頼性などを評価するための書類です。金融機関から事業計画書の書式を渡され、その書類に今後の事業や想定される収入の見通し、返済計画を記入して提出します。
金融機関はその他の書類と事業計画書の内容を照らし合わせつつ、審査を行います。自分たちで作成が難しい場合には、税理士や専門家に作成のサポートを依頼することも有効な手段です。
また、作成に関する不明点などがある際には、曖昧なままにせず、金融機関の担当者に相談してみましょう。
審査の際に必要になるもの

個人名義では、次の書類が必要です。
- 本人確認書類(運転免許症など顔写真が付いた身分証明書)
- 住民票
- 納税証明書(住民税・固定資産税・所得税など)
- 収入確認ができる書類(確定申告書2~3期分、源泉徴収票など)
- 個人事業主の方は事業計画書
- 担保とする不動産に関する書類(公図、建物図面、地積測量図、登記済権利証(登記識別情報)など)
- 印鑑類(実印・引き落とし口座がある金融機関の届出印・印鑑証明書)
本人確認書類に記載されている住所と現在の住所が異なる際には、公共料金の領収書や住民票の写し(原本)などで住所証明が必要です。
また、担保不動産の提供者が申込者と異なる場合、担保提供者が債務を保証する物上保証人、連帯保証人として契約を結ばなければなりません。申込書とは別に保証会社がいる際には、保証会社に対しての同意書に申込者とともに自署・捺印を行い提出するケースもあります。
法人名義では、次の書類が必要です。
- 法人の代表者の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きの身分証明書)
- 納税証明書
- 2~3期分の決算書
- 商業登記簿謄本もしくは履歴事項全部証明書
- 事業計画書(事業計画書で法人の将来性の説明が必要なケースも有)
- 担保とする不動産に関する書類(公図、建物図面、地積測量図、登記済権利証 または、登記識別情報など)
- 印鑑類(代表者の実印・会社の印鑑・引き落とし口座のある金融機関の届出印・印鑑証明書)
個人名義と法人名義の書類に関しては、あくまでも一例です。各金融機関で必要書類が異なる可能性があるため、詳細については、申し込みを検討している金融機関に確認しましょう。